セミナー情報
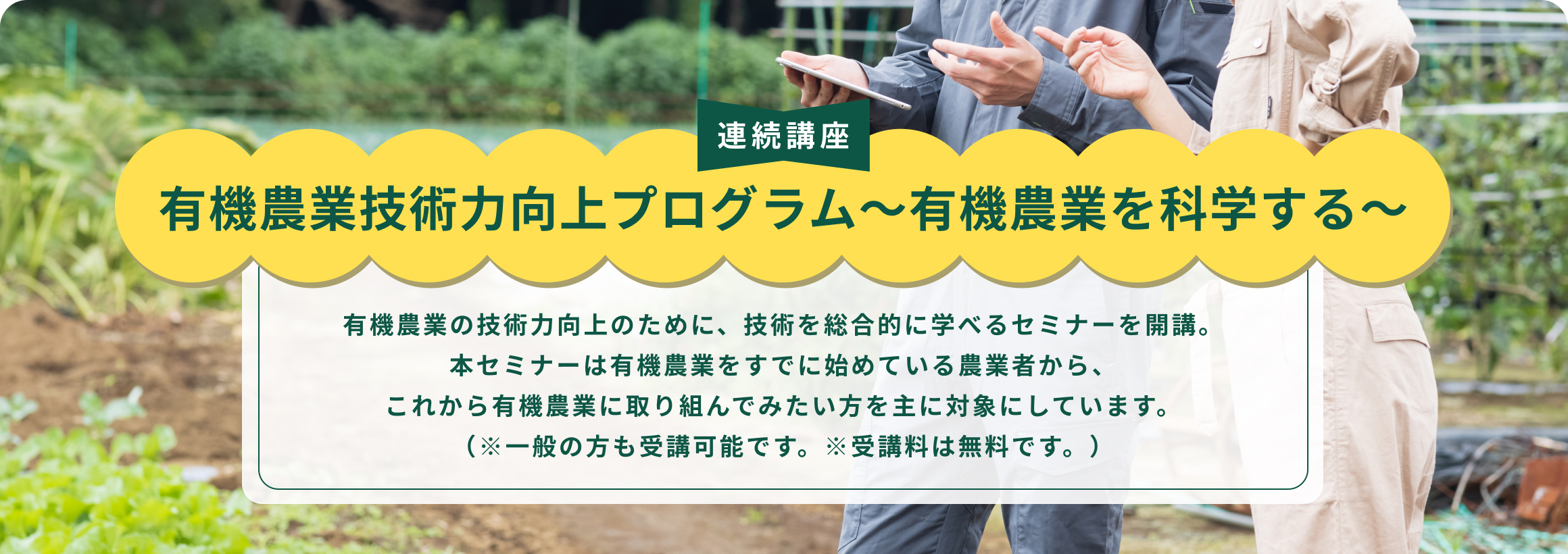
セミナー概要
| 開講時期 | 2025年2~3月 (オンラインで開催) |
|---|---|
| 受講料 | 無料 ※受講後のアンケートにご協力ください。 |
| 定員 | 最大100名まで |
| 申し込み方法 | 各セミナーの申し込みフォームからお申し込みください。ひとつのセミナーからお申し込みが可能です。 |
※セミナーごとの詳細情報や日程は順次オープンしていきます ※内容等が変更になることがありますのでご了承ください。(本事業は農林水産省・有機農業新規参入者技術習得等支援事業を利用しています)
こんな方におすすめ!
-
これから始めたい!
これから有機農業を始めてみたいけど、どこから勉強していけば良いのかわからない。幅広くお話を聞きたい。
-
できるようになりたい!
有機農業を実践しているけど、栽培がうまくいかない。栽培技術や経営などを専門家や農業者から教わりたい。
-
とにかく学びたい!
各分野で活躍している講師たちのお話を聞きたいけど、機会がない。費用が高くて、講座に参加できない。
現在申し込み可能なセミナー
土壌微生物の多様性について
基本的な土づくりの話に加え、微生物の活性等にも言及した内容
2月25日(火)15:00~16:30
オンライン
※お申し込み後、開催日の前日までに参加者のメールにセミナーのリンクをお送りいたします。
-
講師:横山 和成 氏
株式会社DGCテクノロジー -
1959年生まれ。株式会社DGCテクノロジーチーフリサーチャー/元 立正大学 地球環境科学部特任教授。研究分野は、複雑系科学、土壌微生物生態学、植物病理学。北海道大学大学院農学研究科修了。米国コーネル大学農学・生命科学部およびボイストンプソン植物科学研究所客員研究員を経て、農水省管轄独立行政法人・中央農業総合研究センター情報利用研究領域上席研究員などを歴任。農学博士。システムの多様性と安定性について幅広く研究する。著書に『食は国家なり! 日本の農業を強くする5つのシナリオ 』ほか『図解でよくわかる土壌微生物のきほん』監修。
有機栽培(水田)における雑草管理のポイント
有機栽培における雑草対策・管理について総合的に学ぶ内容
3月10日(月)15:00~16:30
オンライン
※お申し込み後、開催日の前日までに参加者のメールにセミナーのリンクをお送りいたします。
-
講師:岩石 真嗣 氏
公益財団法人自然農法国際研究開発センター -
公益財団法人自然農法国際研究開発センターは、食料の安全性の確保、生産の省エネルギー化・低コスト化、資源の有効利用及び農山村の活性化の観点に立ち、地域の実情に応じて自然の生態系を利用した持続可能な生産技術体系の研究開発とその国内外における普及を図ることにより、自然環境の保全、農業・農村の振興ならびに安全かつ良質な農産物の供給に資することによって、社会における健康的な食生活の一層の定着促進に寄与することを目的とした組織。昭和60年(1985)11月13日、農林水産省から財団法人として認可、その後、公益法人法施行に伴い、平成24年(2012)4月1日に内閣府より公益財団法人として認可され現在に至る。
多品目農家が伝える各種野菜の有機的管理について
20年以上の有機農業を営むプロ農家が伝えるさまざまな野菜の有機的管理手法を学ぶ内容
3月12日(水)15:00~16:30
オンライン
※お申し込み後、開催日の前日までに参加者のメールにセミナーのリンクをお送りいたします。
-
講師:山木 幸介 氏
三つ豆ファーム 農場長 -
黒ボク土と呼ばれるフカフカの黒土が広がる台地、千葉県山武市にて20年以上有機農業を営み、栽培の経歴は100品目以上。さまざまな野菜の有機的管理経験をもとにみなさまのお困り事にお答えします。これから有機農業に参入したい方で不安をお持ちの方はふるってご参加ください。(栽培品目:ジャガイモ、玉ねぎ、人参、キャベツ、ブロッコリー、葉物野菜、大根、レタス、ゴボウ、長ネギ、ナス、枝豆、トウモロコシ、里芋、落花生、オクラ等他)
受講に関して
| 申し込み方法 | フォームから必要事項を記入の上申し込みください |
|---|---|
| オンラインセミナー | 申し込み後、開催日の前日までに参加者のメールにセミナーのリンクをお送りいたします。 オンラインセミナーではチャットによる質問も可能です。(全ての質問に回答できない場合があります。)通信費は自己負担となります。 |
| キャンセル | セミナー申し込み後、キャンセルご希望の場合は、事務局までご連絡ください。 |
| 注意事項 | 録画・録音はご遠慮いただいております。 |
| ご協力 | セミナー受講後に、アンケートのご協力お願いします。 |
